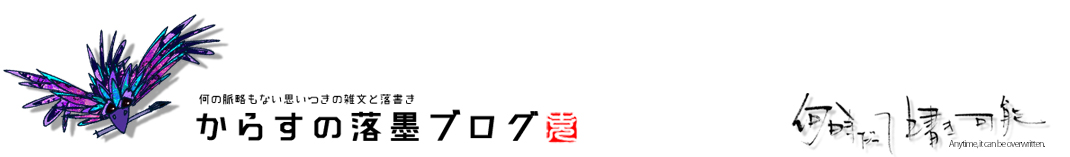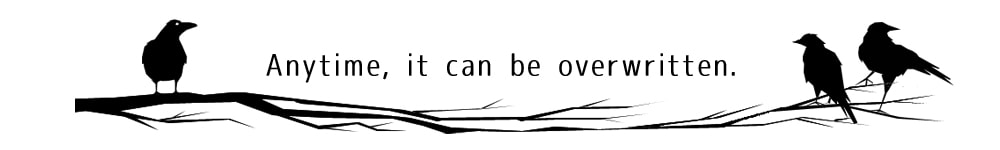
何故、それほどまでにそのトランペットの響きは美しいのか?
何故、それほどまでにその歌声は、心の奥底にしみ込むのか?
1950年代、ウエストコーストのさわやかな風に乗って颯爽と現れた感のあるジャズ界のアイドル、チェットベイカー。 デビューしてまもなく『Chet Baker Sings』というアルバムが大ヒットして、その名を世に知らしめ、ジェームスディー ンにも似た全盛期のビジュアルと、おしゃれで、クールで、青春の光と影を映したその演奏は、一時期、マイルスデイビス をも凌ぐ程の勢いでした。
![]()
しかし、当時のジャズ界に蔓延していた薬物に、身も心も侵されてしまいアメリカのジャズシーンから姿を消してしまいます。 その後、薬物地獄から生還し(実際は生涯依存したままだった)16年ぶりの復活を遂げ、ニューヨークのジャズシーンに現れた時の佇まいは、その壮絶な生き様を物語るような、まさに捨て犬の風貌。
しかし、そこから非業の死を遂げるまでに聴かせてくれた、トランペットとその歌声は、「生まれてすみません」というフレーズを発しながらも、常に月見草の美しい花を僕の心に咲かせてくれました。
![]()
復活時の風貌が衝撃的だったものの、この爺さんの演奏は、何故か「青春の光と影」の匂いを残したまま、よりいっそうの厭世観を放つもので、どちらかというと晩年の演奏の方が個人的には好きなのです。
おそらくこの爺さんは、思春期の感受性を亡くなるまで持ち続ける事の出来た稀な人だったのでしょう。やはり表現するという事はテクニックも去ることながら、伝える力とそれに添付するリアリティーが物を言うのでしょうね。
![]()
世間の風をまともにくらいながらも、酒と女と薬物に溺れ、金や名誉や権威からは遠くはなれた場所で、クソみたいな人生を歩んだ、チェットベイカー。しかしその魂はけして醜いものでは無かったはず(けして賞賛はしておりません)。
![]()
思春期の感受性(世の中のあらゆる事象を何の先入観もなしにありのままに感じ得る心のあり方)を持った精神が、社会の荒波に出て成長して行く過程とはいったい何んなんでしょうか?
この資本主義の世の中を生きて行く上で必要とされる、効率性、生産性、安全性等を身につけて行く過程の中で、すべての事象は言語化しつつ理論武装されていく。 その結果、自我の鎧をより強固にし、世間的には偽りの協調性を示しつつ上手く立ち回る事が精神の成長とするならば、その成長とはいったい何なのでしょうか?
![]()
社会の泥沼の中(自身の自我も含む)で、蓮の花を咲かせる事は至難の技です。 しかし、チェットベイカーの咲かせた月見草の白い花は、今でも僕の心の中で揺れ続けています。
![]()
晩年のチェットベイカーを記録した映画「Let’s Get Lost」は、ドキュメンタリーとしてとても上質な作品となっており、その醜態をありのままに晒す生き様は、ある種の感動を呼び一見の価値有りです。
![]()