映画の内容や結末よりも、二人の役者の掛け合い、映像、音楽の、すべての要素が心地よく響き合い、なんとも言えない気持ちよさを味わうことのできる、ハリウッド映画には珍しい繊細で気品のある作品でした。

ちょっと忙しくなると途端にブログの一つもあげられなくなる、ポンコツすぎるジジィな僕なのですが、映画を観に行く時間は何故かあるわけで、行ってきましたよ《グリーンブック》。
本当は前前回の記事の流れから《サマータイム》の聴き比べをやるはずだったのですが、一ヵ月以上も空き、なんかテンションも下がってしまった(知らんわっ!)ので、今回はこの映画の感動のテンションが下がらぬうちに…。

いつもの様に
「この映画、好きそうだから観に行く?」
と、かみさんに誘われ、内心ではいつもの様に
「俺の何をわかっとると言うのだ!俺はそんな簡単に好みを見透かされる様な、底の浅い人間ではない!」
と思いつつ映画館へ。 そしてこれまたいつもの様にかみさんの予想通り、僕の好みにピッタリハマって涙しながらえらく感動してしまった、底の浅すぎる僕が、いつもの様に薄っぺらい感想を書かせて頂きます。
ネタバレ、バリンバリンなので、観に行かれる予定の方は読まないでちょうだいね。

舞台は、南北戦争から100年近くたっても尚、南部では有色人種を差別するとんでもない悪法《ジム・クロウ法》が存在していた1960年代のアメリカ。
2歳からクラシックピアノの英才教育を受け、天才的な才能を発揮。 その他の教養もすべて身に着け、当時凄まじい差別を受けていた側の黒人でありながら気品に満ちたインテリミュージシャン、ドン・シャーリー。
一方、アメリカ移民の中でも底辺の生活を強いられていたイタリア系移民のトニー・リップ。
その減らず口と有無を言わさぬ腕力で、ニューヨークの高級クラブで用心棒として働いています。 家族思いの情に溢れたナイスガイなのですが、ガサツで教養もなく、気品の欠片もないチンピラ気質。
貧乏ながらも家族とそれなりに幸せに暮らしていたトニーは、ある時勤め先のクラブが改装のため一定期間閉鎖され、その間、他の仕事を探さざるをえなくなります。
そこに舞い込んできた仕事が、天才ピアニストの二ヵ月に及ぶ南部ツアーの運転手兼雑用係兼用心棒というお仕事。
当時の他の白人同様、トニーも黒人に対して強い差別意識を持っていたため乗り気ではなかったのですが、雇い主、ドン・シャーリーの強い要望もあり、報酬も要望通りに受け入れてくれたこともあって、仕方なくこの仕事を引き受けます。
気品と教養をまとった黒人天才ピアニストの雇い主と、ガサツで無教養の雇われ白人運転手という、幾重にもねじれまくった奇妙な組み合わせのオセロコンビの自動車による南部ツアーの旅が始まるのです。

ここで運転されるアメリカンクラシックカーは、あまりにも美しく気品のあるターコイズグリーンの《キャデラック ドゥビルセダン》。
このロードムービーの心地よさの一因ともなっているこのターコイズグリーンのキャデラックは、この映像を作るにあたって絶対に欠かせないアイテムだったのでしょう。この車の持ち主にふさわしい、後部座席に座るシャーリーの気品に満ちた佇まいとそのファッション。一方、運転席のトニーは、そのコントラストで、より一層ガサツに見え、高級ベンツに乗るヤクザそのもの。
この対比がとてつもなく面白く、観る者の興味をそそります。

僕は1950年代から1960年代にかけてのいわゆるモダンジャズが大好きで、結構聴き込んでいるのですが、この映画を観るまでは、ピアニスト、ドン・シャーリーをまったく知りませんでした。調べてみるとクラシック畑の住人で、当時活躍したジャズメンとは、ほとんど交流が無かったそう。(唯一の共演はデュークエリントン!この人の懐の深さはさすがです。)
酒と煙草とドラッグにまみれた当時のビ・バップのジャズメンの奏でる音楽とは相いれなかったのではないでしょうか?
映画の中のトリオ編成は、ピアノ、コントラバス、そしてチェロという独特の編成。これでスタンダードのジャズの演奏をやると、ジャズでもなくクラシックでもない不思議な音楽になっており、最初は「何なんだこの音楽は?」と戸惑って聴いていたのですが、物語が進むにつれ主人公のオセロコンビの関係性がなじんでくればなじんでくるほど、この音楽も僕の耳に馴染んできて次第に心地よくなり、ジャズであろうがクラシックであろうがどうでもよくなってきたのです。 自宅に戻ってユーチューブで改めて聴いてみたのですが、素晴らしすぎる!
レイ・チャールズのカバーで世に知られることとなったジャズのスタンダード中のスタンダード《我が心のジョージア》のドン・シャーリーの演奏は、僕がこれまで聴いてきた《我が心のジョージア》のなかで最も気品と優しさに満ちた響きを奏でており、ゲイの方たち(物語の終盤で明らかになります)特有の哀愁がダダ洩れなのです。
やはりドン・シャーリーは、当時の黒人ミュージシャン達とは全く異なる景色を観ていたのでしょう。
物語が進むにつれ、また、二人の響きが深くシンクロしてゆくにつれ、黒人と白人、教養と無教養、気品と下品、裕福と貧困。これらの境界線が曖昧になってゆく過程に、ドン・シャーリーのジャンルを越え、普遍性を帯びたピアノの響きが非常に効果的に使われるのです。白人文化の音楽理論の英才教育を徹底的に叩き込まれた黒人、ドンシャーリーの奏でるジャズ系のポピュラーミュージックの響きは、この映画のすべてを物語っているようでした。

話を物語に戻します。
旅の初めは、二人の人種や育った生活環境、価値観の大きな乖離にぎくしゃくした関係が続くのですが、旅が進むにつれ(南部に入れば入るほど酷い差別を受けるドン・シャーリー)数々のトラブルに見舞われ、そのトラブルを二人で凌いでゆくにつれ、それぞれの持っていた固定概念が次第に溶けて行くのです。
この映画の面白いところは、白人トニーが一方的にシャーリーを蔑んでいたわけではなく、黒人のシャーリー側も、低級層で無教養のイタリア移民、トニーに大きな偏見を抱いていたところ。 人間である限り、白人であろうが有色人種であろうが、人は常に人をカテゴライズし、自分より下位とみなしたものを差別してしまう生き物なのです。
その最たるもの、根源的なものが、腕力で勝る男性がいまだに世界を支配している現状なのでしょう。

またしても話がズレたので映画に戻しますと、
そんな当時のアメリカ南部を黒人が旅をするためのガイドブック(黒人が利用できるホテルやレストランなどを記したもの)が、この映画のタイトルとなった《グリーンブック》と呼ばれていたものなのです。
上流社会の白人に請われて演奏をしているミュージシャンに、その白人たち自身が不条理な差別をしていることに気づかないほどに、絶対的な認識としてインプットされている《白人至上主義》とはいったい何なのでしょうか?
今現在、アメリカ大統領として暴れまわっているドナルド・トランプおじさんの思想の根っこは、この《白人至上主義》で、それを支持する大多数のアメリカ人も《白人至上主義》の思想の持主なのでしょう。
これはアメリカ人の、もしくは白人のDNAにまで組み込まれた本音なのです。しかしながら、そのなかでも良識ある白人の人達は、その本音を偽善で隠さずにあからさまにし、その野蛮性を自己認識することから、丁寧に問題解決を進めつつ世界と対峙しているのでしょう。

またまた話がズレまくってゴメンナサイ。
ドン・シャーリーは、様々な迫害を受けながら南部の奥深く入ってゆきます。ここでさらにややこしい事実を僕たちは知ることとなるのです。
ある町で演奏を終えた夜、シャーリーは一人で街を彷徨い、白人青年との逢瀬を警官に見つかり留置所に収容されます。そう、シャーリーはゲイだったのです。
そうとわかるまでのシャーリー役のマハーシャラ・アリの演技。これが素晴らしすぎたのです。あからさまなゲイの演技ではなく、滲み出てくるような同性愛の方の独特の色気、所作。これが完ぺきで、本物なのか?と、見紛うほどでした。
映画ではこの辺り、それ以上表現することは避けていたのですが、その帰り道、トニーとの言い争いで、激しい雨の中、車を降りてしまうシャーリー。それを追うトニーに向かって叫ぶシャーリーの本音は、涙無くしては聞けなかったのです。
「僕は黒人でもなく白人でもない! 何処に行っても自分の居場所がない。自分の演奏は上流階級の白人の慰めもので、僕自身の評価ではない! 僕は何者なんだぁ!!」
と、涙ながらに夜空に向かって訴えるシャーリー。
旅の途中、奴隷制度はなくなっても以前と同じような劣悪な環境の中、広大な木綿畑で働かされ続ける大勢の黒人たちに遭遇。 この黒人たちが生涯、絶対に乗れないであろう豪華なキャデラックに佇む同じ黒人のシャーリーを なんとも言えない眼で見つめる黒人労働者達。
このシーンは、シャーリーの心の中の原風景(更にゲイであることも含んで)を映しているようで、シャーリー自身のアイデンティティーの不確かさを表しており、観ている僕たちもドキッとするほど、心をえぐられるのです。

重たい題材を扱っている映画にもかかわらず、このオセロコンビの軽快な言葉のやり取りや、頻繁に織り込まれている心温まるユーモアのシーン、そしてバックに流れるドン・シャーリーの繊細なピアノの響きも相まって、全編を通してなんとも心地の良い風が吹き続けるのです。
旅の途中、手紙など書いたことのないトニーが、最愛の妻 ドレレス に対して頻繁に約束の手紙を書きます。 苦戦しているトニーから、その手紙を奪い取って、見た時のシャーリーのセリフ、
「これはツギハギの脅迫状なのか?」
以後、トニーの手紙は、シャーリーの語る素晴らしく詩的で美しい言葉を羅列したラヴレターとなって、最愛の妻 、ドレレスに届くこととなるのですが…。
キャデラックの車内でのやり取り。
当時流行りの黒人音楽を何一つ知らないシャーリーに対して
「黒人のくせにリトル・リチャードも、アレサ・フランクリンも知らないのか?」
と攻め立てるトニー。更に当時大流行りの《ケンタッキー・フライドチキン》も食べた事のないシャーリーに、無理やり手づかみで食べさせるトニー。そしてまんざらでもないシャーリー。
このような旅の日常の取るに足らない交流を通して、それぞれが持っていた、かたくなな固定概念や先入観が次第に溶けてゆき、知らず知らずのうちにお互いの心の響きが深くシンクロしてゆくのです。
そして旅の終わり、シャーリーはトニーの妻 ドレレスや 家族と共にクリスマスを迎え、ハッピーエンドで終焉を迎えます。
その挿入歌の一つに、僕の大好きなナットキングコール《 ザ・クリスマスソング》が流れた時、意味もなく涙があふれだし
「もう終わるとーーっ! もっと浸っときたいーーっ」
と心で叫ぶ僕なのでした。

人種の違いや生活環境の違い、貧富や地位の差。本当の人間の価値はそう言った外的要素をすべて越えて互いにシンクロ(響き合う)したとき、人間が人間としての尊厳を感じあえることの素晴らしさにあるのではないのでしょうか?
しかしながらそれとは裏腹に、個々の人間の自我は、すべてのものを損得や見かけの美醜で判断し、さらには勝手に自分達より低俗と見極めた人や物事を差別し蔑むもの。その人間のサガをしっかりと自己認識したうえで、それらすべてを無意味なものとして忘れ去り、ただただ人々や森羅万象に響きを合わせ、その直感で生きていけるようになれたなら…。
そのようなことを踏まえたうえで、あえて黒人差別の厳しいアメリカ南部に演奏旅行に臨んだ音楽家ドン・シャーリーの態度は、対峙する相手に対して憎悪や復讐の念を向けるのではなく、差別する側の野蛮性を自身で気づくことのできる単なる鏡としての役割をになっての旅であり演奏だったのでしょう。
あのマハトマ・ガンジーがそうであってように。

はたして、自身のアイデンティティー、主義主張、民族の誇り、ナショナリズム、重くて堅苦しいこれらのものは人にとって必要なのでしょうか?
人間であることの尊厳を響き合わせることが出来るなら、最終的にはそれのみで事は足りるのではないでしょうか? その響きをシンクロさせることの大きな役割を果たせる一つのアイテムが音楽であり、その他の芸術なのでしょう。
映画《グリーンブック》は、ストーリー的にはよくあるハリウッド映画だったのですが、このようなことをしみじみと思わせてくれる、良質なロードムービーだったのです。
トニー役のビゴ・モーテンセン、シャーリー役のマハーシャラ・アリ。
二人とも本当に素敵な役者さんで、この二人の放つ音のハーモニーがこの映画を
心地よいものにした大きな要因だったのではないでしょうか?

最後に、ドン・シャーリーの素晴らしすぎる音楽をお聴きください。
超お勧めの、《Water Boy》と、 我が心のジョージア《Georgia On My Mind》。
どうしてこんなに涙が出るほどに優しく心地よい音楽を奏でられるのでしょうか? すべてスタインウェイのピアノで演奏される名曲の数々は、様々な美しい風景を僕たちに見せてくれます。
今まで知らんかったのがなさけない!!

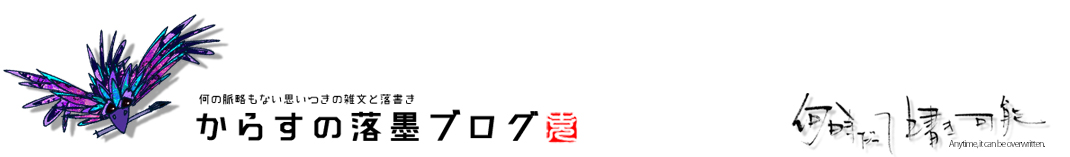

久しぶりに映画館に行って観てきました!
このブログでオススメならばと。
気持ちの良い涙がじわーっと来る映画でしたね。
このままずっと終わってほしくない気持ち、分かります!!!
帰りは雨が降っていました。
電車で15分で帰れるのに、我が心のジョージアを聴きながら、
わざわざバスに揺られ、1時間ほどかけて帰りました。笑
それにしても、ロード・オブ・ザ・リングの方とは、、、、
どー考えても同一人物には、まったく思えません!
役者さんって凄い∑(゚Д゚)