《キネマの神様》に続く沢田研二主演映画《土を喰らう十二ヵ月》。 昭和の時代に書かれた水上勉の料理エッセイを中江裕司監督が映画化。暖衣飽食の令和ニッポンに《食する》《愛する》《育む》《生きる》《死ぬ》の本当を今一度問うた舌触り最高の作品!
密かに楽しみにしていた映画《土を喰らう十二ヵ月》。封切り日朝一番に柚子ジンジャーソーダを片手に観賞してまいりました!

多少のネタバレあります。まだ見ていない方はご覧になった後でお読みください。
曹洞宗の開祖・道元の記した『典座教訓(てんぞきょうくん)』の教えを基本とした精進料理を 幼少期に禅寺で徹底的に仕込まれた経験を持つ作家の水上勉が、畑で育てた旬の野菜を材料にして、心のこもった惣菜をつくる様を 心のこもった映像、音声で、人や自然との触れ合いを丁寧に描いた日本映画ならではの秀作でした。
映画のオープニング、編集者で恋人役の松たか子演じる《真知子》が運転する乗用車が、都会から主人公ツトム《沢田研二》の住む信州の山里へと向かうシーンから始まります。
車の走行音と共に、アップテンポのリズムに乗った、ちょっとフリージャズっぽいサックス、トランペットのアドリブフレーズが心地よいBGMが流れます。
この作品の音楽担当はなんと大友良英‼ 皆様ご存知、朝ドラ《あまちゃん》や大河ドラマ《いだてん》等の音楽を手がけたジャズギタリスト。都会の喧騒から静かな山里へと移る変化と対比をこの音楽で感じさせるシーン。 僕個人的には大友良英は大好きなミュージシャンなのですが、この映画の肝である《山里の生活音》《山里の自然音》が素晴らしすぎて、今回の大友良英の音楽は効果的ではなかったように思いました。 できれば木で造られた楽器(ビオラ、チェロ、コントラバス等)の音を入れてほしかった(保守的なつまらないジジィですみません)。

大友良英の音楽が邪魔だと思えるほどに、全編を通した《生活音》《自然音》が心地よすぎて、時に人の会話の音声さえもいらないなぁ…と思えるシーンもいくつか。
ちょっと違和感があったのは音楽と不必要な説明セリフ。なかでもツトム《沢田研二》が脳梗塞?の病に倒れ意識不明の重体から意識が戻った刹那、傍にいた看護婦が、(突然倒れ、救急搬送され、三日間意識不明だったこと等)の情報を意識が戻ったばかりのツトムちゃんに矢継ぎ早に大声で喋っているシーン。
「三日間生死を彷徨って脳みそボーッとしとるワシに、そんなん色々一気に言われてもわかるかい!!」
と、ツトム、さらには皆さまになり替わって不肖わたくしが心の中で叫んでおきましたのでお許しを。
そんな小さなことが吹き飛ぶほどにツトム《沢田研二》の精進料理を作りながらの信州山里でのシーンが映像、音声共に素晴らしすぎた。

作品のストーリをつたえる会話を最小限に抑え、四季の移ろいの映像と生活音を淡々とつたえる心地よさ。そして何よりもツトム《沢田研二》のナレーションの心地よさ(原作・土を喰う日々の文面ほぼそのままに語られておりました)。沢田研二さん(今回あえてジュリーとは書きません)の声質がもうドンピシャで内容もさることながらその響きが美しすぎた。
旬の野菜を収穫するときの茎を切る音。
根野菜を掘り出す音。
湧き水で泥を洗い流す音。
風が通りぬける音。
鳥のさえずり。
虫の声。
梅の花びらが開く瞬間の無音
ツトム《沢田研二》のナレーションの声音。
無垢の木のまな板の上で野菜を切る音。
竈のマキの燃える音。
ご飯の炊ける釜の音。
野菜を煮込む鍋の音。
板の間を歩く足音。
衣の擦れる音。
料理皿を無垢のテーブルに置く音。
野菜の咀嚼音(本当に上手そうに食べる食いしん坊の真知子さん)
ツトム《沢田研二》のナレーションの声音。
遠くで聴こえる蛙の鳴声。
ランプに灯を灯す音。
原稿用紙に万年筆を滑らす音。
本のページを開く音。
梢がざわめく音。
雨音。
雷音。
粉雪の無音。
夜の静寂の無音。
ツトムの、言葉では表現できないあらゆる感情が発露する微表情の無音。(ナチュラルに年を重ねた爺さんの佇まいに、顔に拍手!)
そしてそして、
生活音と心地よく響きあう感情を抑えた沢田研二さんのナレーションの声音。
ツトムの暮す茅葺の家屋には、科学素材(プラスチック、セラミック、ビニール等)で出来た生活用品が殆んどなく、自然素材(木、紙、陶器、木綿等)の道具で囲まれて生活しています。それらを使用するときに発せられる様々な音(響き)と屋外の自然の音(響き)が美しくシンクロし、その音(響き)にツトム《沢田研二》のナレーションの音(響き)が重なった時、何とも言えない至福感を味わえるのです。 野心や、夢や、願望をかなえた時の喜びとはまったく別次元の、何でもない日々の暮らしの中にある煌めきと喜び。令和ニッポンの現状。機械音、電子音の騒音に囲まれ、心の隙間や不安をスマホからの情報で埋め尽くし、現実(リアル)と仮想(バーチャル)の狭間、イベントづくしの刺激の中で、凄まじいスピードで疲弊してゆく僕達は、何を思ってこの映画を観るのか? 日々の生活で感じ得る至福感を捨ててまで追い求めないといけない夢や願望とは…。

禅宗の修行僧の一日の大半は、寺の作務。 極端に言えば、坐禅行よりも作務の中にこそ真の《瞑想》があるという高僧もいるほど。日々の暮らしのそれぞれの作務を一心に勤めることが《悟り》の一番の近道。
高僧が悟りを開いたきっかけが、
「雨だれの音を聴いた刹那」
「カラスの鳴声を聴いた刹那」
「喝!」の一声の刹那」
というエピソードがあるように理屈ではなく音(響き)こそが、眠っている脳の松果体を刺激し、隠された能力が開花されるのではないでしょうか? 《悟り》なんて大層なものではないにしろ、常に自然が発する音(響き)と共に身も心もシンクロして生活していれば、「人は至福の中で生きていけるのか」と感じさせてくれた映画の中の自然音と沢田研二さんのナレーションの声音だったのです。

そしてこの映画の一番の見どころは、前半の《食する》《生きる》から、後半の《死》という《死生観》に繋げていく所。 ひとり暮らしの義理の母の死別や生死を彷徨う大病を経験し、死の恐怖を味わったツトム《沢田研二》の至った境地は、継続する時間の流れを生きるのではなく、その瞬時瞬時を永遠と感じて生きること。 これこそが曹洞宗の《死生観》。
「天国、地獄、輪廻転生、あるのかないのか等、死後の世界の心配をする時間があるのであれば、この瞬間を十全に生きろ! 喝!」
と、天に諭されたのか、ツトム《沢田研二》は以後、日々死を思った(メメントモリ)生活に変化し、毎日就寝時「皆さん、さようなら。」とつぶやいて眠りにつきます。そして翌朝の目覚めの第一声が「今日も生きている。」
手放せなかった13年前に亡くなった妻・八重子の遺骨も、森の池?に散骨。そう、筍の皮のように土に戻すのです。
《食する》《愛する》《育む》《生きる》《死ぬ》これを五感で十全に感じることの幸せは、この世に生まれた意味のすべてなのではないでしょうか?
この作品はイメージを感じる映画。そのためのストーリー、登場人物。 理屈で理解する映画とは一線を画した五感で感じる映画なのです。

その他のキャストも味のある役者さんが揃っており、中でも恩人、禅寺の和尚の娘役・壇ふみさん。NHK《連想ゲーム》以来久しぶりに見ましたが(嘘つけ)、最高の演技でした。この、《舌触り》《手触り》《肌触り》のよい映画の床の間に飾られた《一輪の茶花》のような控えめな、美しさ、さりげなさ。 壇ふみさんのような内面の精神性から滲み出る《気品》と《色香》を同時に感じさせてくれる女優さんもほとんどいなくなりました。
大工役・火野正平さんもいい味を出してました。自転車《チャリオ》で各地を旅する、NHK・BS『にっぽん縦断 こころ旅』は、番組開始当初は大好きで見ていたのですが、かみさんの「こんな女ったらしのジジィのなにが面白いん?」の一言で我が家では終了。調べてみるとこの番組いまだに続いおており、密かな人気番組のようです。 あと、義理の弟役・尾美としのりさんの演技はいつ見ても秀逸。落語家の瀧川鯉八さんの出番は2カットだけ。特大の遺影は笑わせて頂きました。 義母役の奈良岡朋子さん、小さな掘立小屋で暮す変わり者のババァを好演。
世間が言うほど、孤独死とは本当に不幸な死なのでしょうか?
この婆さん、きっと良い死に顔で亡くなったことと思うのですが…。鯉八が用意した大きな遺影の婆さんの口から、「何見てんだよっ!」という声がたしかに聴こえたことから、大往生だったと確信しました。

そしてエンディングロールに流れる楽曲《いつか君は》。 全編を通して奏でられた生活音と自然音のハーモニー。 その響きをそっくりそのまま歌い上げたような沢田研二の歌唱。心地よいビブラートの余韻を浴びて心洗われ、この映画で教わった《死生観》を胸に、一汁一菜、粗衣粗食を実践しながら、余生を美しく送ろうと誓ったジジィひとり、その舌の根も乾かぬうちに福岡キャナルシティ―・ラーメンスタジアムのギトギト濃厚醤油ラーメンと黒焼き飯をたらふく食し、家路についたのでした。
久々の更新。そして次回の更新は何時になるかわからない、しがないブログを最後まで読んで頂き感謝感謝でございます。
それでは皆さん、さようなら。

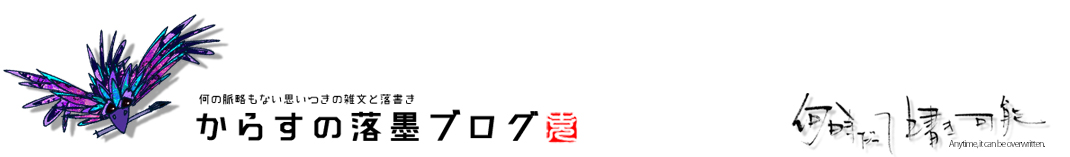
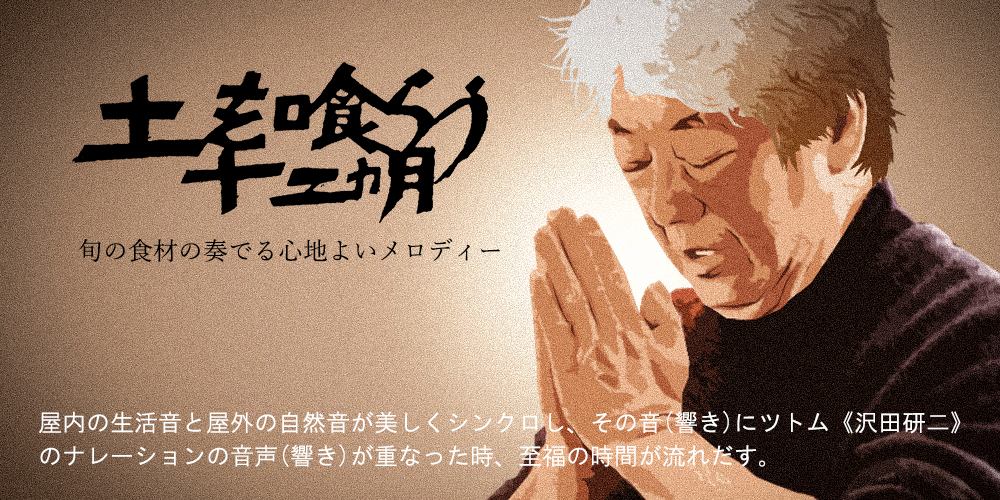
お久しぶりのブログ、待ってました!
時々チェックしていたんですが…
お元気そうで、良かったです。
「土を喰らう十二月」の感想、拝見しました。
この時期に、しみじみと心に沁み渡る映画の様ですね。
五感に響く音や、色や、匂いなどなどは何よりも心を満たしてくれますよね。
そういう満足度こそ、人間の本来の姿だと思います。
仕事柄、縄文や弥生時代の物に触れることが多く古代人と現代人の違いが多い様で少ない事に気付かされてます。
いつの時代も人は、変わらないものなんでしょうね。