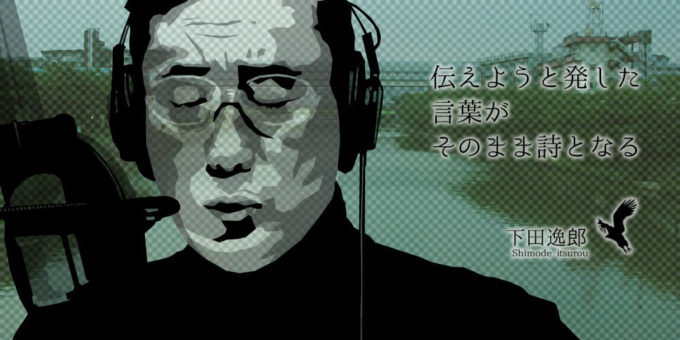
恋歌の吟遊詩人、下田逸郎。その歌声は何故か無意識の領域に響き渡る。
時々、無性に下田逸郎の歌声を聴きたくなる。難しい言葉使いは一切なく、淡々と語るそのラブソングは、男性の中に眠る女性性、女性の中に眠る男性性をくすぐります。
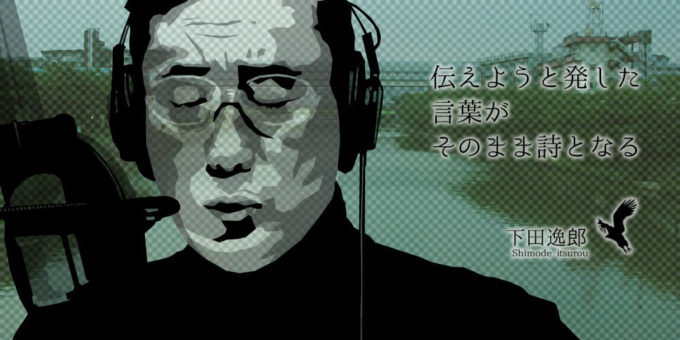
時々、無性に下田逸郎の歌声を聴きたくなる。難しい言葉使いは一切なく、淡々と語るそのラブソングは、男性の中に眠る女性性、女性の中に眠る男性性をくすぐります。

いやぁ〜っ、今年のM−1決勝、面白かったし、レベルもすこぶる高かった。決勝に出て来たすべての漫才コンビは、その特徴を生かしたネタを披露してくれましたが、安定感抜群の王道漫才コンビ『銀シャリ』の優勝は、異論のないところ。

《中山うりの原風景》何の情報もイメージも持たない幼児が、はじめてチンドン屋に遭遇したときの風景。それをそのままピンホールカメラで映し撮った世界観。ミクロの世界から、いつの間にかマクロの世界に飛躍する普遍性。
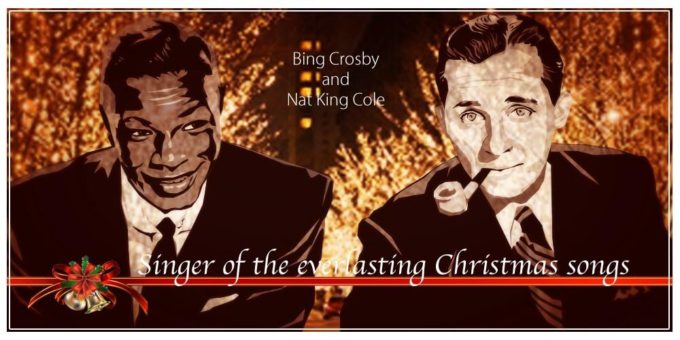
街はクリスマスイルミネーションで彩られ、そこかしこからクリスマスソングが流れだす一年で最も華やかな時節となりました。イベントの予定等入れずに、音楽を楽しみながら、それぞれが(ファンタジー)空想にふけるクリスマスもあって良いのでは?

出場歌手が決定すると、毎年のように疑問視される紅白歌合戦の選考基準。歌謡曲の消滅した10年程前から、すでに選考基準は定まらず、その存在意義さえ疑われる昨今、今一度考えてみましょう。『NHK紅白歌合戦とは何か?』
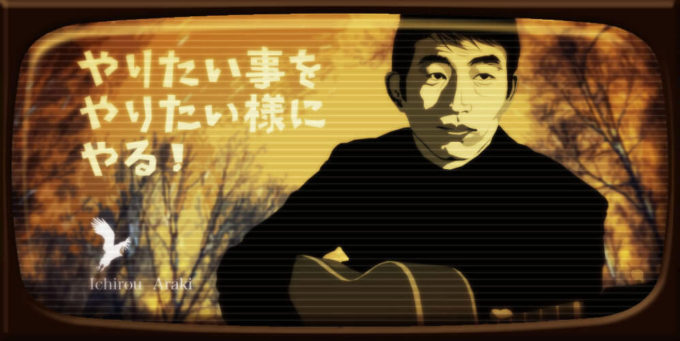
もはや名前を言っても誰もわからなくなってしまった、荒木一郎。同世代の加山雄三が太陽とするなら、荒木一郎は銀色に輝く月として、今も夜空を照らしています。
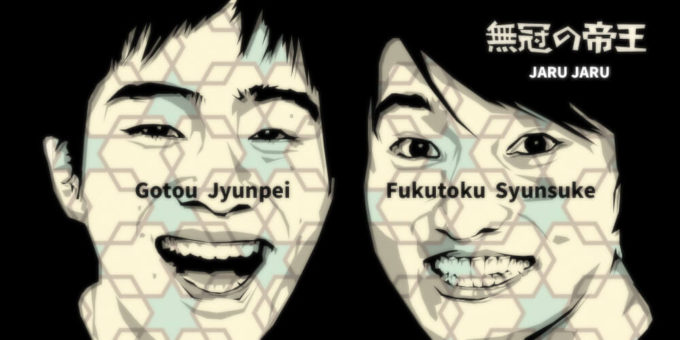
ネタの独創性、発想力、演技力、身体表現力、練習量。どれをとってもピカイチの、ジャルジャル。そのジャルジャルの時代は何時になったらやって来るのか?

もっと、もっと、もっと、再評価されて良い『ザ・ピーナッツ』。 その抜群の歌唱力とハーモニーの美しさにおいて、いまだにこのデュオを越えるグループは出現しておりません。

世の中は、所有出来る物や約束出来ることなど何一つ無く、それだからこそこの世界は永遠で美しいことを教えてくれたのは、友部正人でした。
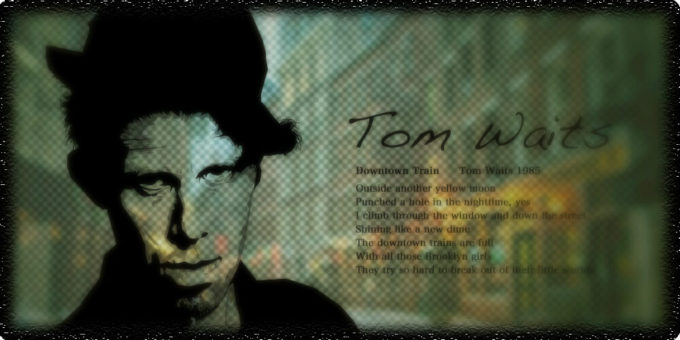
トムウェィツの放つ、ジンタやチンドンを匂わせる多国籍ごった煮ミュージックは、流浪の民ジプシーの哀愁にも似た、 とらえることの出来ない原初の感情の「それ」に似たもの…。