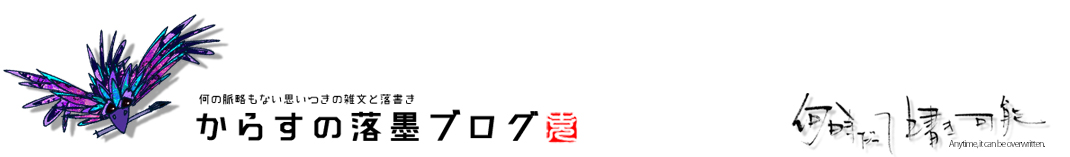嫌煙運動家が見たら卒倒しそうな全編喫煙シーンの映画。しかし、その煙草の煙のようなもの(嘘)も、人生には必要不可欠な要素ではないのかと全編を通して語りかけくれる、いつまでも浸っていたい最高に心地よい肌触りの物語なのです。
愛煙家が犯罪者の如く蔑まれる昨今、「そこまで虐めなくてもいいんじゃねぇっ!」と叫びたくなるような迫害を受けながら、隠れるように煙草を吸い続けるお父さん達は、とってもお気の毒。
20年ほど前に止めてはいるものの、若い時分1日5〜60本程吸っていたヘビースモーカーだった僕にしてみれば身につまされる思いなのです。はたして口角泡を飛ばしてまくしたてる程、煙草にそこまでの害はあるのでしょうか? 喫煙と肺がんの因果関係も、いまだ明確に証明されておらず、よく解らんのですよこれが……。と、これ以上語ると嫌煙運動家に本格的に虐められそうなので本題に入ります。
![]()
それこそ、僕が超ヘビースモーカーだった20年以上前のお話。
いつもの様に徹夜明けで仕事を納めた帰り、これまたいつもの様に何の予備知識もなく、何がかかっているのかも知らずに飛び込んだ、ミニシアター《テアトル天神》。そこで大当たりした映画の一つが、この《スモーク》だったのです。
この映画は、《マイ・フェイバリット・シネマ》ベスト5に確実に入る程の作品。以前書いた《トム・ウェィツ》の記事の中でも少し紹介しているのですが、前回の記事の日本映画《幸福のスイッチ》に出てくる日本人のおばあちゃんと、この《スモーク》のラストシーンに出てくる黒人のおばあちゃんがソックリな事(本当なんだって!)を発見。嬉しくなって、久々にこの映画を思い出します。
最高に素晴らしい映画なので、古い映画なのですが改めましてのご紹介。
![]()
《嘘》とは?《真実》とは?《罪》とは?《善意》とは?
人は、騙したり騙されたりを繰り返し、いわゆる煙(スモーク)に巻き巻かれながら世の中を渡ってゆくもの。その過程で様々な《嘘》を繰り返します。「俺は断じて嘘をついた事なんかない!」なんて言っている人は、その時点で一番の大嘘つき。
《嘘》にも様々なものがあります。良い嘘、悪い嘘なんてハッキリ分けられるはずもなく、ありとあらゆる感情の集合体の発露として《嘘》が出現し、それはいつだって曖昧模糊としたもの。
《真実》だって怪しいものです。人はとんでもないイマジネーションを駆使して生きています。人それぞれの捉え方感じ方で《真実》は玉虫色に変化し、たった一つの《真実》なんてものは存在しないのです。(もちろん物理的なものは別ですが、量子力学的にはそうでもない事も…)
その曖昧模糊な煙草の煙(スモーク)のような《嘘》か《真実》かわからないものを絶妙な距離感と、暗黙の了解の中で粋に操り、さりげない優しさがスクリーンから滲み出て来るような映画がこの《スモーク》なのです。
![]()
アメリカの作家・ポール・オースターが、1990年、ニューヨーク・タイムズ紙に寄稿した《オーギー・レンのクリスマス・ストーリー》という短編小説をベースに、ポール・オースター本人が脚本も手がけ、ウェイン・ワン監督が映画化したもの。
物語は、アメリカ・ブルックリンを舞台に、3人の男の人生の軸が偶然(必然?)にふれあい、からみ合いながら進んでゆきます。
まずは主役のオーギー・レン(ハーヴェイ・カイテル)。
ブルックリンの街角の小さな煙草屋のオーナー。店の常連客は、たわいもない会話を楽しみにこの店にたむろしています。オーギー・レンはベトナム帰還兵。いわくつきのカメラ・キャノンAE-1で10年間、毎日同じアングルで自身の店のファサードを写しており、その数なんと4,000枚にも及びます。
次は、その店の常連客で友達の作家・ポール・ベンジャミン(ウィリアム・ハート)。
7年前の銀行強盗事件に、妻・エレンと、お腹にいた子供が巻き込まれ、同時に亡くしており、以来、小説が書けなくなっています。そんな状況の中、街をボーっとして歩いてた折、車に轢かれそうになった所をたまたま通りかかったラシード(偽名)という少年に助けられます。ラシードと名乗る少年、実は犯罪がらみの怪しい金を持って逃げ回っており、本名をトーマス・コール (ハロルド・ペリノー・ジュニア)というのです。 過去に大きな傷を持つ、この三人の男性が出会った所から物語は大きな展開を見せます。
![]()
ここからはバリバリのネタバレありです。ダラダラとあらすじを書きますが、観ていない方は是非、映画を先にご覧下さい。
オーギーの煙草屋に閉店間際に訪れるポール。閉めかけた店を再び開けてくれたオーギーに、煙草の代金を支払っている時、ふとレジスターの横に置いてあるカメラを見つけます。何を撮っているのかと訊ねると、10年間1日も欠かさずに自分の店のファサードを撮っているとオーギー。興味をっ持ったポールは、その写真を見にオーギーの自宅へ。
春夏秋冬、雨の日も雪の日も風の日も欠かさず、毎日同じ時間、同じアングルで煙草屋のファサードを撮った写真を適当に流しながら見ていたポールに、ゆっくり見なければダメだと諭すオーギー。この営みをライフワークにしているオーギーにその意味を訊ねると、毎日同じ時間、同じアングルで撮った写真なのだけれど、同じものは一つとしてないと言います。太陽の日差しの角度、明るさ、通りすがる人々の顔ぶれや服装。そういったゆっくりとした時の流れと同じように、ゆっくりとした心持ちで写真を眺める事をポールに勧めるオーギー。
![]()
世界の片隅の何でもない街角の風景を、どのような眼差しでどのような心情で眺め、そして、その一瞬一瞬にどのような感情を置いてゆくのかで、その人の未来が作られてゆき、更には過ぎ去った過去さえも変えられるのだと、オーギーは語っているように、僕は感じたのです。
物語は始まったばかりなのですが、僕はのこのシーンが大好きなのです。ハーヴェイ・カイテルとウィリアム・ハート、この二人の役者ならではの肌触りの良い空気感。二人のそこはかとない、ふかしたジャガイモのような笑顔が最高なのです。
![]()
写真を眺めてゆくうちに、亡くなったポールの妻・エレンが映っているのを発見。撮影の時間がエレンの通勤時と重なっていたため、何枚かエレンが映り込んでいたのです。
すべて事情を知っていたオーギー。事件に巻き込まれる直前、エレンはオーギーの店に立ち寄っていました。店を出る時間がもう少し早かったか遅かったかすれば…。色々な意味を含めて、この写真をポールに見せたかったのでしょう。泣きながら写真を見つめるポールの肩を黙って抱きしめるオーギー。
部分的な視野しか持ち得ない僕たちからすれば、間違いなく「神はサイコロを振る」と思えてしまうような出来事。
![]()
場面変わって、ポールの仕事場のアパートの一室。
いきなりラシード(偽名)が訊ねてきます。車に轢かれそうになった所を助けてもらったお礼に、カフェでレモネードをおごった帰り、何時でも寄ってくれとアパートの住所を渡していたのです。
2日程泊まって去って行ったラシード(偽名)は、帰り際、札束の入った紙袋を本棚の裏へ。 数日後、ラシード(偽名)の伯母と言う黒人女性が訊ねてきます。そこではじめてラシード(偽名)の本当の名前をトーマス・コールと知るのです。12年前、母親を事故で亡くし父親も失踪。 その父親を探しに家を出てさまよっているトーマス。
そんなトーマスはとうとう、父親が経営する、街はずれの潰れかけたガソリンスタンドを探し当てます。父親のサイラス(フォレスト・ウォテカー)の左手は義手。母が亡くなった事故の時運転していたのは父親のサイラス。その時、片腕を失っていたのです。
正体を明かさず、バイトとして雇われるトーマス。この時のトーマスは、父とわかってサイラスとの会話をするのですが、こまっしゃくれた言葉の端々に何とも言えない感情を挟みます。置き去りにされた子・トーマスと、片腕を無くし子供を置いて失踪してしまったサイラス。しかしトーマスは、夕方迎えに来た新たな妻と小さな赤ん坊を見る事に。
どちらも過去に深い傷を背負ったまま、何とか厳しい現実を生きているのです。この辺りのセリフのセンスは流石、ポール・オースター。この人の小説の文体そのものなのです。
![]()
一方、オーギーの店には、元カノのルビー(ストッカード・チャニング)が訊ねてきます。ルビーは、オーギーの兵役中、オーギーを裏切って他の男と結婚。すぐに離婚してしまうのですが、その一人娘(ルビーはオーギーとの子だと主張)が悪い男に引っかかり薬中になったうえ、子供を身籠っているとのこと。何とか助けたいと、昔のよしみでオーギーにお金の無心に来たのです。ハバナ葉巻の密売のため、蓄えていたお金を全て使い果たしていたオーギーは、お金を用立てすることが出来ずルビーを追い返します。
![]()
ポールのアパートには、再びトーマスが訊ねてきます。ポールは伯母さんが訊ねて来た事、偽名を使っている事、本棚の紙袋の大金の説明を迫ります。トーマスが言うには、不良仲間が強盗していた所に巻き込まれ、その時に不良仲間が落としていったお金を拾って逃げ回っていると。
一時、トーマスをバイトとして預かってくれるようオーギーに頼みこむポール。男気をだして快く引き受けるのですが、トーマスはそのバイト中、大変なミスを犯します。オーギーが洗面台の下に隠していた密売するハバナ葉巻を不注意の水漏れで台無しに。オーギーの信用と大金が失われます。
仲介に入ったポール。本棚の後に隠された紙袋の大金はそのままオーギーの元へ、一度は断るもののポールの説得により受け取るオーギー。
そんなトーマスをかくまっているポールのアパートに、居場所を嗅ぎ付けた二人の不良仲間が。運良く外出していたトーマスが帰宅中、道路からアパートの部屋の異常を察知し警察に通報したため、腕の怪我程度で済んだポール。トーマスは再び父・サイラスの元へ。
![]()
そんな折、再びルビーがオーギーの店へ。頼る人も無く、娘とお腹の子供を救いたい一心で、説得するため、娘が住んでいるアパートに一緒について来て欲しいと懇願。仕方なくオーギはルビーと共に娘のアパートへ。
オーギーを父親だと紹介するルビーに悪態の限りを尽くしてののしる薬中の娘。身籠っていたお腹の子供も既におろしており、愕然とするルビー。諦めてアパートを出るルビーとオーギー。二人が去った後、娘は複雑な表情で涙を流します。
悪態の限りののしる娘の汚い言葉の裏側に、母に対する愛情と「助けて欲しい!」の叫び声を読み取るオーギー。
諦めて故郷に帰ろうとするルビーにオーギーは、トーマスから受け取った紙袋の大金の全てを渡し、娘を再生施設に入れるよう諭します。驚きのあまり言葉にならず泣きじゃくるルビー。
最後に一つだけルビーに訊ねるオーギー。
「あの娘は本当に俺の子か?」
ここで正直に答えるルビー。
「わからないの。あなたの娘かも知れないしそうでないかも…、フィフティ・フィフティね。」
ここで少しの間があってオーギーは、限りなく優しい笑顔でルビーを見つめ、そして去ってゆくのです。 オーギーにとって、自分の中での一つの区切りをつけるためのお金でもあったのでしょう。しかし、真実がどうであってもそれ以上深く詮索しない優しさ、気遣い。
その時の自身の行動に、欺瞞や憎しみの感情を乗せるのか、それとも寛容と微笑み(愛)を乗せるのか…。もしかしたら人の運命や宿命は本当に決まっているのかもしれません。しかし、その人生の時々にどのような想いを置いてゆくのかは、100%自由なのです。その想いの置き方次第で、決っている運命や宿命さえも、ひょっとしたら変えられるのかもしれません。
![]()
話を戻します。
トーマスの行方を探し当て、サイラスのスタンドに出向いたポールとオーギー。トーマスが偽名を使っており、サイラスにあなたの実の息子だと明かすポール。いきなりの事に取り乱し、トーマスを殴りつけてしまうサイラス。
場面変わって、ガーデンテラスのテーブルを囲って無言でランチをする、ポール、オーギー、トーマス、サイラスとその妻と赤ん坊。
いたたまれない空気感の中、ポールとサイラスは煙草を勧め合います。サイラスの妻の腕の中で眠る赤ん坊の頭を撫でるトーマス。この場面、そこそこの尺はあるのですが、最後まで皆無言。 場面転換の後、映し出されるシーンはブルックリンの街並を縫うようにして静かに走る鉄道列車。
これが何故か美しい!
人生の様々な局面で人々の感情が織りなす色と光。そして季節を映す街の景色。その中を何時もの様に淡々と列車は走り、時は流れてゆくのです。
![]()
そしていよいよラストシーン《オーギー・レンのクリスマス・ストーリー》。
これまでダラダラと書いたストーリーは、このラストシーンを見せるための壮大な前振り。すべては、このシーンを見せたいがためのものだったのです。
作家ポールに久々の原稿依頼。ニューヨーク・タイムズから、クリスマスにちなんだ短編小説を求められます。なかなかアイデアが思いつかないポール。煙草を買い求めに寄ったオーギーの店で何となくその話をすると、ランチをおごってくれるなら俺のとっておきのクリスマスの実話を聞かせるとオーギー。
その日の昼、食堂で二人は向き合ってランチをとった後、煙草を吹かしながらオーギーが語り始めます。
![]()
オーギーがまだ煙草屋を始めた頃、黒人の少年がエロ雑誌を万引きして逃げ去ります。あわてて追っかけるオーギー。途中で息が切れ、追うのを諦めるのですが、道端で少年がおとした財布を見つけます。
お金は入っていなかったのですが、満面の笑みで映った卒業写真とおばあさんと一緒の写真、そして運転免許証。それらを眺めているうちに、小さなときは幸せだったのだろうが、ブルックリンのダウンタウンでまともに育つはずがない、今や麻薬漬けの日々なんだろうなぁ、と考えているうちに、何だか可哀想になって警察に届ける気持ちも失せてしまい、そのまま財布はテーブルの隅に置きっぱなしに。
時は流れ、その年のクリスマス。
何もすることがなく、一緒に過ごす人もいないオーギーは一人淋しくポツンと部屋に。と、眼の片隅にすっかり忘れていた少年の財布が…。 たまには良い事をしようと思いつき、免許証に書いてある住所のアパートに届けてあげようと出かけます。
同じような建物が建ち並ぶ団地で、何度も迷いながら目的の番地へ。呼び鈴を鳴らしてしばらくするとけっこうな年寄りとおぼしき女性の声で「どなたです?」と聞こえます。オーギが少年の名前を言うと、おばあさんは少年が帰って来たものと勘違いをして、沢山の鍵を次々と開け、
「きっと来てくれると思っていたよ、クリスマスの日におまえが私を忘れる訳がないもの!」
と満面の笑みで出迎えます。
オーギーは一目でその老婆が盲目である事を悟ります。有無を言わさずオーギーを抱きしめる老婆。咄嗟の事で何を言っていいのかわからず、思わずオーギーは
「そうだよおばあちゃん、クリスマスだもの!」
と答えてしまったのです。
抱き合った感触と匂い、声質、気配で盲目の老婆が孫である少年ではないと気づかないわけはありません。しかし二人は、その一瞬、暗黙の了解の内にある種のゲームを始めるのです。
誰もいない一人っきりの、ありのままの現実のクリスマスを生きるよりも、二人だけのファンタジークリスマスを楽しむ事にしたのです。
そしてその日一日だけの《おばあさんと孫の年に一度のクリスマス》が始まります。
おばあさんの矢継ぎ早の質問にオーギーはでっち上げの答えを次々と返します。
「やっと煙草屋の就職がきまってね、いい感じなんだ、その店」
「良い子と巡り合えてね、今度結婚するんだ」
老婆はすべて信じているフリをしなが、
「よかったねぇ」
「わかっていたよ、お前の事だもの、きっといつか上手くいくはずだって」
と本当に嬉しそうに頷くのです。 そのうちお腹が空いて来て、チキンやスープを街で買って食卓に並べるオーギー。老婆も隠し持っていたとっておきのワインを空け、立派なクリスマスディナーに。
楽しく食事を終え、老婆は話し疲れて、うたた寝を始めます。そしてオーギーはトイレへ。そのトイレの片隅に何台かの新品の箱に入った高級カメラ・キャノンAE-1(おそらく少年の盗品)が。生まれてこのかた、カメラを撮った事も無ければ、盗った事もなかったオーギーなのですが、何故か一台のカメラを懐に。食事の後片付けを終えた後もすっかり寝入っている老婆をそのままに、少年の財布をテーブルに置いて静かに立ち去るオーギー。
その後3〜4ヶ月後にもう一度、カメラを返しに老婆を訊ねるオーギー。しかしその部屋には違う住人が。おそらく亡くなってしまっていたのでしょう。生涯最後の老婆のクリスマスを一緒に過ごした、《なりすましの孫》オーギー。その上カメラまで盗んでしまったオーギー。しかしそのカメラは、その後4,000枚もの《芸術作品》を残すこととなるのです。
《オーギー・レンのクリスマス・ストーリー》はここで終わります。
![]()
ここまで黙って聞いていたポールは、その話すべてがオーギーの作り話なのではと、疑います。しかし瞬時に考え直すのです。その物語が真実であれ嘘であれ、聴き手の感受性がすべてなのだと。
《信じる者が一人でもいれば、その物語は真実になる》
この物語そのものと、話し手、聴き手の相互関係。《嘘》、《真実》、《罪》、《善意》。そのすべてが時間と空間を行き来し、人の感情を絡めながら世の中は巡っています。物事は多面構造で成り立ってるのです。嘘と真実、罪と善意は表裏一体。絶対真実や絶対正義なんてものは存在しないのです。
存在するのは人の心の感受性。その感受性がそれぞれの人生を形成してゆくのだと、映画《スモーク》は僕に語りかけてくれたのです。
![]()
オーギーが食堂で物語を語った後、映画はその物語をサイレントのモノクロ映像で再現します。映画の歴史の中で、これほどに美しく切ないラストシーンを僕は他に知りません。俳優、ハーヴェイ・カイテル最高の演技。この5分間のラストシーンを見るだけで入館料を払う価値は十分ある映画なのです。
そして、このラストシーンのバックに流されるのがトム・ウェイツの名曲《夢見る頃はいつも》。もう、涙なくしては観れないのでした。
トム・ウェイツ《夢見る頃はいつも》
鐘楼の中にはこうもりたちの巣
荒れた野原は霧にぬれる
俺を抱きしめた あのつややかな腕
愛を誓った あの日々はどこに消えた
あの腕や あの言葉はどこに消えた
懐かしく そして悲しい気分だよ
草原はいつもやさしく そして緑
想い出の中から 僕が盗み出すのは
遠い日のぼく 過ぎ去った時の記憶
そうさ 夢見る頃はいつも
けがれなんて知りはしないよ
夢にあふれ 無邪気に歌っているんだよ
夢にむせび 無邪気にわらっているんだよ
そうさ 夢見るころはいつも
ぼくたちは決して別れやしない
きみとかわしたまぶしい約束の言葉
そういって恋人のくびからかけたペンダント
でも誓いを破ったのはぼくで
あの娘のハートを砕いたのもぼく
静かな墓地の中 駆けずりまわり
笑いころげた友人たちとぼく
あの時ぼくらは誓いあったね
みんなずっと一緒だよ
死がぼくたちを引きはなすまで
死ぬまでみんな一緒だと
![]()